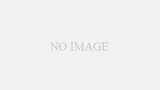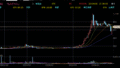なぜ読書を再開したのか
私はもともと読書をすることが好きでしたが、高校生になってスマートフォンを買い与えられてからは、だんだんと本を読まなくなっていきました。
そして、大学に入るころには、ソーシャルゲームや動画視聴などに夢中になりすぎて、読書は殆どしなくなってしまいました。
そのせいで学業にも悪い影響が出ましたが、何とか卒業はできました。
そして社会人になってからしばらくして、再び読書に取り組むようになりました。
とはいえ、往時の集中力はすっかり衰えてしまったので、十数分ほど読んだら集中力が切れてしまい、ほかのことをやってしまいます。
最大の要因はやはりソーシャルゲームです。比較的最近に始めたものから長い間プレイしているものまで、5つ掛け持ちをしています。
そしてゲーム以外にも、外国語の勉強や一時期は絵の練習もしていました。
一日にすることがこれだけ多いと、結局どれも中途半端になったり、意欲が消えてしまったりして止めてしまうことになります。
加えて、やらないと「いけない」という観念に取りつかれてしまえば、好きで始めたつもりのことでも日々ストレスを感じてしまうようになってしまいます。
そうなってしまっては非常に良くないので、取り組むことの取捨選択をしたり、メリハリをつけたりする必要があります。
あれは諦める/もうしない、あれは時間に余裕ができたらまた一からやる/後回しにする、AとBとは同時並行でやるが、優先するのはAの方、…といった具合です。
最近読んだ本
「降伏論」という本を読んだ(電子書籍版)のですが、その本の最初の方で、未完了のタスクを放置することが自身のパフォーマンスを著しく下げることについて書かれていました。
やらないといけない仕事ややりたいことがあったとしても、ほんの少しの未完了タスクのせいで集中できなくなってしまうという趣旨だったと思います。
つまりついこないだまでの私は、それに近い状況であったと言えるのではないでしょうか。
「降伏論」でいうところの未完了タスクとは、仕事や趣味、勉強などといった「重要なこと」に対する、ゴミ出しやメールの返事などの「些末なこと」ですが、私の場合は、「重要なこと」が何個もあって、それらが相互に悪影響を及ぼし合っていた、ということも、また一種の未完了タスクの蓄積なのだと思います。
(ある一つのこと、例えば外国語の勉強をしていると、それ以外のこと、例えばイラスト練習や簿記の学習などが気になってしょうがなくなる、あるいはこれらの計画を完遂できるかどうか不安になってしまうということ)
(それらに加えて、ゴミ出しや掃除、メールの確認などの、それこそ些末なことが後回しにされて、次第に堆積していくということ)
最後に
読書の時間を意識してとるようにしたことで、有用な知識・知恵が身について、生活の改善などにつながることを実感しているところです。
ただ私はもともと読書好きなので、再び読書の習慣を取り入れることに抵抗はなかったのですが、本を読む習慣が今までなかった人や読書に対して苦手意識を持っている人などの場合は、何らかの工夫が必要になるところだと思います。
最後までお読みいただきありがとうございます。